外国株式への投資の必要性とオススメできるETF銘柄 『全世界へ分散投資』
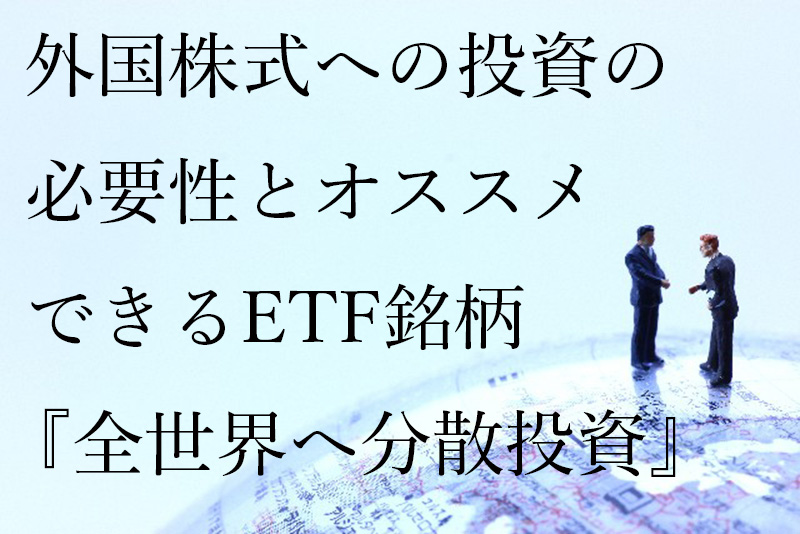
前回、国内株式へ投資するなら日経平均連動ETFを超長期で保有する『株式投資初心者』でお伝えした通り、資産運用のポートフォリオ(リスク資産)に国内株式を組み入れる場合、国内株式市場全体に投資できる、日経平均連動ETFがオススメだと述べました。
しかし、いくら幅広く国内株式市場全体に投資をしたとしても、それだけではまだ理想的なポートフォリオだとは言えません。
特に、1980〜1990年代の日本経済バブルと崩壊を経験した人や、失われた20年と呼ばれる長い経済低迷期・デフレ期を経験してきた私たちであれば、国内株式だけに投資をするリスクを十分に理解できるはずです。
そこで今回は、外国株式投資の必要性と予測の難しさを考えていきます。
GPIFや欧米の年金基金も外国株式へ投資しているのには意味がある
国内株式ですら将来を読むことが不可能と言われているのに、詳しく知らない馴染みのない外国株式に投資する必要があるのかと疑問に思う人は多くいます。
ですが、日本の政府年金投資ファンド(GPIF)も欧米の主要年金基金も、自国外(外国)の株式に投資しています。
外国株式投資は収益機会拡大とボラティリティ軽減の効果がある
なぜ、このように国内の株式だけではなく、外国の株式にも資金を振り分けて投資しているのかというと、海外の資産に投資する手法の国際分散投資は、収益機会の拡大とボラティリティの低減という2つの効果をもたらすからです。
収益機会の拡大効果は、国の株式市場全体のリターンは、国の経済全体のリターン担っているので、日本よりも成長率が高い国の株式の方がリターンを多く得られる可能性があるからです。
また、ボラティリティの低減効果は、景気を循環するために回復や好調、減速などが異なる国の株式に投資することによって、分散効果が得られるということになります。
国内株式はまだバブル期の株価を超えていない
例えば、バブル期の株価の最高値は約4万円でした。その頃に株式投資を始めた(当時はETFはありません)とすると、バブル崩壊後から現在まで、投資収益はマイナスとなります。
しかし、外国株式の利回りを見てみますと、マイナスどころか大幅なプラスになっています。
これらのように、国内株式だけではなくて外国株式にも投資をすることで、収益機会を拡大することができます。
国内株式と外国株式の株価は連動しているわけではない
長期の投資をしていると、国内株式が年間を通してマイナスのリターンの時期が何度かあります。
だからと言って、外国株式も国内株式に連動してマイナスのリターンになるということではありません。
これは、よくニュースなどでNY市場の上昇を好感して東京市場も上昇などの報道があり、短期的に日米の株式市場の連動性があるように思いますが、長期的に見てみるとあまり連動性は高くありません。
ですが、リーマンショックのように、大規模な金融危機が起これば、世界中の株式市場が一気に下落するということも確かにあります。
外国には日本を上回るリターンを得れる国が多数あるが見極めるのは困難
外国では日本を上回る成長力を持つ国が多く存在しています。
それにより日本の株式市場全体から得られるリターンが、世界の平均から大きく下回っていた時期も多くありました。
その時に国内株式だけに投資していたら、外国株式の大きなリターンの機会を失っていたことになります。
そういったことを補うために、資産を海外の株式市場にも投資し、運用することを強くオススメします。
株式市場には数え切れないぐらいの外国株を買える銘柄が上場している
近年では、ブラジル・ロシア・インド・中国のBRICや、アジア諸国など、エマージング・マーケットへ投資する投資信託やETFも株式市場に続々と登場しています。
長期に渡ってそれらの外国株式に投資を行う場合、将来的に発展する海外の株式市場からのリターンを狙う必要があります。
どれだけ優秀なアナリストでも超長期にわたる予測はできない
20年や30年後にどこの国が成長しているか、それに反映してどの株式市場に動きがあるのかを予測することは、絶対に不可能だと言われています。
例えば、10年ほど前は「中国・ブラジル・ロシア」などはこの先何十年も目紛しい成長を続けると、大多数の人が予想していましたが、現在ではその成長は減速しており、それに伴い、株価も大幅に下落してしまっています。
一時的なブームに惑わされ、証券会社やアナリストの情報に乗せられて、狭い範囲で外国の株式に資金を回すのは賢明な投資ではありません。
外国株式の個別銘柄になると予測はさらに困難
仮に、投資すべき市場を予測して確信があったとしても、個別銘柄になるとさらに選択が困難です。
アメリカの企業であるアップルやグーグルなどでしたら、比較的予測しやすいかもしれませんが、先進国でも新興市場の個別銘柄や新興国の個別銘柄などは、情報が英字であったり、最新の情報などが手に入りにくく、外国株の個別銘柄の目利きは国内株式以上に難しいです。
予測困難な海外市場への投資を行うのであればバランスよく全世界に投資
外国株式への投資は非常に難しいのですが、国内株式だけでは縮小する可能性があるので、日本の株式からのリターンを補う目的で、海外の成長からリターンを得るためには、バランスよく海外の株式を保有することが大切になってきます。
しかし、世界中の株式市場で個別銘柄をチェックして選んで、バランスよく投資することは、よほどの資金がない限り不可能です。
将来必ず発展すると市場を予測することはとても困難ですが、世界の株式市場に投資することが、資産運用のためには重要になってきます。
そうすると、どのようにすればいいのでしょうか?
それは、世界の株式市場全体を指標化した投資信託かETFへの投資を行うのです。
GPIFや欧米の年金基金も、この方式で国際分散投資をしています。
『MSCI オール・カントリー・ワールド (ACWI) 除く日本』のベンチマークに投資
日本以外の先進国と新興国を組み合わせた全世界(フロンティア国は除く)を対象にした株価指数『MSCI オール・カントリー・ワールド (ACWI) 除く日本』というベンチマークがあります。
そして、そのベンチマークに連動する投資成果を出すように運用されているETF『上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554)』という商品があります。
上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554)は約70か国に投資できる銘柄
- 種類:国内ETF
- 運用会社:日興アセットマネジメント
- カテゴリ:外国株式
- 取引通貨:円
- 信託報酬:0.3%(年率・税抜)
- 配当:あり
- 純資産総額:35億円
上記の銘柄を購入できる証券会社
このETFが連動している指標の主な構成は、
- 先進国: 24か国
- エマージング: 21か国
- フロンティア: 25か国
これらの国の時価総額上位約85%をカバーしています。
単純に分散投資しているわけではなくスタイル別で細分化されている
また、上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554)は、北米・ヨーロッパ・アジアなど地域別、国別、バリュー・グロース・高配当などスタイル別で細分化して投資されています。
この指標に追随する金融商品を購入することによって、普通の市民であっても世界の株式市場全体に投資することができ、分散効果の恩恵が得られます。
まとめ
- GPIFや欧米の年金基金も外国株式へ投資しているのには意味がある
外国株式投資は収益機会拡大とボラティリティ軽減の効果がある
国内株式はまだバブル期の株価を超えていない
国内株式と外国株式の株価は連動しているわけではない - 外国には日本を上回るリターンを得れる国が多数あるが見極めるのは困難
株式市場には数え切れないぐらいの外国株を買える銘柄が上場している
どれだけ優秀なアナリストでも超長期にわたる予測はできない
外国株式の個別銘柄になると予測はさらに困難


